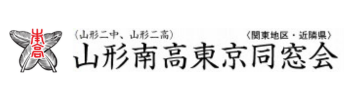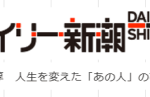皆さん、お元気ですか。私がネパールに初めて足を踏み入れたのは平成4年でした。以来、思い出深い体験や冒険を経て33年が経ちます。記憶の正確な時にその辺りを纏めておきたいと思い今回の文にしました。本欄に個人的な体験を載せるのは本意では無いのですが、私自身の記録としての意味合いもありますので帆容赦ください。今回は番外編です。
皆さんはネパールと言う国をご存知でしょうか。ヒマラヤ山脈が走っている山国で世界最高峰のエヴェレストを持つ国と、この辺りまで知っていれば御の字ですね。もう少し詳しく書きますと、国土の面積位は14万7.500㎢の小国でありますし、人口は2913万7000人と面積も人口も日本の四分の一ほどしかありません。また、世界の国旗の形状は四角形なのですが、彼の国の国旗は三角形を上下に並べた形で、その三角形の中に月と太陽が描かれております。
前述した通りヒマラヤ山脈を抱えておりますので、山国との印象が強い国ですが、南部にはインドの平原と陸続きの原野も有しており、虎や象そして鎧サイなどの珍しい動物たちも生息しております。特筆すべき大人物は仏教の開祖と言われるお釈迦様(ゴーダマ・シッダルタ)の生まれ故郷もこの国に有るのです。私が、彼の国を訪れたのは今から30年程の昔になりますが、その頃は王様がいて王制が布かれておりました。隣国・中国の影響を受けた毛沢東主義者が各地で暴動を起こし、王制が廃止になったのは2007年5月の事になります。
王制から「ネパール連邦民主共和国」と変わったのですが、2020年12月から国名を「ネパール」に変えております。人々の暮らしは30年前とほとんど変わらず、貧しく衛生状態も良好とは言えません。街の喧騒も相変わらずですが、バイクの増加でむしろ騒音は増大しております。携帯電話が急速に発展し、人々の生活も忙しくなっております。
そんな事は如何でも良いのですが、30年前はこんな小さな王国の中に、もう一つの王国「ムスタン王国」と呼ばれる小さな国が有ったのです。この王国はつい最近まで「鎖国」政策を執っておりまして、出入国には特別な許可証が必要でした。当時はこのパーミットを摂るのが難しく、北ムスタンと南ムスタンとの国境の村カグベニまでしか行けませんでした。カグベニまでは3回も足を運びましたが、北の「ムスタン王国」へ入国することは叶いませんでした。
しかし、ひょんなことから、ムスタンの国王夫妻にお会いする事が出来たのです。平成6年ですから今から31年前1994年の1月の事です。南ムスタンを旅し、帰路に就くフライトは客席が19シートしかない小型機でした。地方の空港は地域の社交場でもあります。世話になったMDSAの方々との別れを惜しんでいた私は、搭乗する順番が最後になりました。乗ったところ王様が私に向かって「ジャパニーズ」と声をかけて来たのであります。
ここでMDSAの事について説明しなければ、何のことか分からないと思いますので付け加えますが、南ムスタンの国境の村カグベニを訪れた私はジョンソン村のホテルに戻り、ウイスキーのグラスを手にニルギリ(7061m)の夕日を見に外に出たのであります。その時「日本の方ですか」と声を掛けられました。驚いて声の方を見れば、馬上にブラウンのダウンを纏った方が優しく私を見ておりました。そして「私は、近藤亨と申します。この地で地区の開発に携っております」との口上が続きました。
当時、ネパールへの支援を志す人々にとって「近藤亨」と言う名はバイブルの様な存在だったのです。新潟大農学部からJICA隊員として農業支援でネパールに渡った氏は、現地の農業スタイルを一変させ、付加価値の高い果実を世に出したのであります。ネパールの人々も「摘果」や「枝打ち」などはこの世のものでは無かったのではと推察しております。私自身、氏の名前は知っていたのですが活動場所がムスタン地区だとは知らなかったのです。退官後はその地にMDSA(Mustang Development Service Association)を立ち上げ寒村の復興に心血を注いでいたのです。
早速彼の事務所を訪問し、持参した梅干しや海苔を持って行ったと思います。酒はたしなまないと言う氏に代わって日本からの研修生が対応してくれました。「そうですか。土木の先生ですか。土木工学の観点から見ればこの辺りはまだまだでしょう」などとの会話から始まり、ネパールへの支援の在り方にも話が及びました。何よりも楽しかったのは氏の勝負事への拘りでした。話の経緯で翌日は「麻雀」をする事になり氏と雀卓を囲むことになってしまった事です。ネパールの奥地での麻雀と言う事でアドレナリンも上がりっぱなしで徹マンになってしまいましたが、翌日は稼いだ金で馬を雇いツクチェ(ジョンソン街道沿いの村)往復の旅に出る事が出来ました。
4日目はムスタンからの帰路です。ジョンソンの飛行場からネパール第二の都市ポカラまでのフライトです。チベットを水源とするカリ・ガンダキ川の河原を平たく敷きならしただけの滑走路は、早朝の風の無い時だけ開かれます。しかも飛行場は現地の社交場でもあるのです。近藤氏が突然「毛利先生、ムスタン国王が見えてますので紹介しましょう」と言って私を国王の下へ案内したのです。ご夫妻でのフライトとの事でご令室も同行されておりました。握った国王の手は柔らかく大きかったですね。
その国王が最後に乗って来た私に向かって「前の席に座れ」と指示を出しているのです。今もそうですが座席指定など無い飛行機なのです。そこは操縦席の後ろで景色の良く見える席でした。席には王の従者と思しき若者が座っておりましたが、彼をどかせてそこに座れと指示を出していたのです。若者が後部座席に移動して来たので、私が前に行くしかありません。恐らくその若者は飛行機に乗るのが初めてで、自分の目でヒマラヤを眺めたかったのかもしれません。私は申し訳なさで落ち着いたフライトを楽しむ事が出来ませんでした。
平成9(1997)年4月4日東京目白の「椿山荘」に於いて「幻の王国・ムスタンの夕べ」なるパーティーが400名もの参加者の下に開催されました。主催はMDSAを率いる近藤氏であります。来賓として挨拶に立った国王は、東京を「非常に機械化された都市」などと評価しながら、ムスタンへの支援の依頼をしておりました。席に挨拶に行き訳を話すと、夫婦で大きく頷き笑顔を返してきました。その時、私の胸に痞えていた申し訳なさが消えたのを覚えています。
あの時の当事者ではなくとも、その主人筋にあたる人にお詫びを口にした事で、詫びの気持ちが伝わったと思ったのであります。その王国も今は無く、ネパールの地方の村として名を残すだけとなっております。今年の10月にはその国の首都だったローマンタンを訪れ、あの河口慧海も拝んだであろう経典を拝みたいと思っております。楽しみです。
令和7年9月21日 毛利