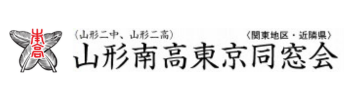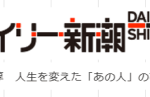皆さん、お元気ですか。
お盆に入り少しは過ごしやすくなりましたね。間もなく蝉の声から虫の声に変わります。焦らずに季節の変化を待ちましょう。などと、虫の音による季節の変化を切り口に、毛利のアドレス帳に載っている方々へBCCにて配信しております。メーリングリスト該当者は外したつもりでしたが、混入しておりましたらご容赦ください。
私が初めて海外に行ったのは昭和61(1986)8月の事ですから、今から40年近くも昔の事になります。フィリピンのセブ島へダイビングに行ったのが最初でした。恐ろしく派手なシャツを着こんでサングラスを掛けていましたね。若気の至りで粋がっていたんでしょうね、恥ずかしい限りです。昔のマニラ空港で保安員に目を付けられ、特別室に連行された事もありました。如何も、「ジャパニーズマフィア」と呼んでましたから、その筋の人と間違われたのだと思います。窓口では仲間が「彼は怪しい者ではない。スキューバダイビングに来た観光客だ」などと弁護してくれておりましたが、見るからに姿かたちは怪しかったですがね。
こんな事は如何でも良いのですが、フィリピン滞在中は南国のスコールに何度も見舞われました。コテージからレストランに至る僅かな距離でも、吹き荒れる爆風と勢い良く降る雨に恐れをなし、スコールが納まるまでレストランに閉じ込められました。ものの30分も経てばスコールは収まり、天には「さそり座のアンタレス」が赤く不気味に輝いていたのを思い出します。スコールに出会ったのはその時が初めてでしたが、「凄い雨だな」との恐怖を覚えました。
過去にスコールの様な豪雨に遭遇したことは三度ほどあります。一度目は「伊勢湾台風」の時の風と雨です。昭和34(1959)年9月25日潮岬に上陸した台風15号が東海地方を総なめにし、日本列島を串刺しに進んだ大型台風でした。山形地方の通過は真夜中でしたが、激しい風と雨により我が家も窓が飛ばされる被害を受けました。停電も重なり走り去る自動車のライトがほの白かったのを思い出します。丁度、中学生の頃でしたね。
二度目は富士山で遭遇したこれまた台風による横殴りの雨です。女流講談師の神田紫さんの富士山講談にお付き合いした時の事です。彼女も「認定特定NPO法人富士山クラブ」の会員で富士山には憧憬が深く、富士山頂での講談を11回(今年の8月8日)も成功させている講談師です。その彼女が主催する頂上講談の観客として同行し、場を盛り上げるのが我々の努めでした。
富士山五合目富士宮口を午後一時に発った我々を待っていたのは激しい雨と風でした。ガイドを勤めていた元富士山レンジャーと名乗る方が「これは台風によるものではない。富士山に懸かっている「笠雲」の影響だ」との説明でした。見れば確かに富士山に懸かる笠雲の端が見えるのです。しかし、その頃南方洋上には台風8号(確か?)が接近し、日本列島へ鎌首を擡げていたのであります。夜来、山小屋には豪雨と風が吹きよせ寝るゆとりすらありませんでした。朝五時に登頂は断念し下山する事になったのですが、下山する我々へ横殴りの雨と風が押し寄せ、中には転倒する会員も出る始末でした。今考えれば「良くぞ無事で下山できたものだ」と奇跡の生還でありました。
三度目は、先日も天皇皇后両陛下が訪れたモンゴルでの豪雨です。先の大戦の折、国際条約(日ソ中立条約)を無視したロスケの侵攻により、捕虜となった日本人の一部がモンゴルにも収容させられました。その頃建てられたオペラハウスなどは今でも首都ウランバートルに残るなど、日本人は多くの足跡を残したのであります。その反面、亡くなった方々も多く、現地にはそれら日本人を悼む慰霊碑が建立されておりました。街を見下ろす高台に巨大な慰霊碑が築かれ、敷地を管理する人も常駐しておりました。
我々は、ウランバートル地区のお祭り(ナーダム)を訪れた後にその地を訪れ、お祈りを済ませたあと帰路に就いたのであります。その時に遭遇した豪雨が忘れられません。本来、モンゴルは雨は降りますが豪雨は少なく川が氾濫する事などめったに無いのであります。それが車の運転すら危険ではと思わせる雨が落ちて来るのです。因みに「モンゴルの河川は全てバイカル湖に注いでおります」と書いた方が地政学的には理解されると思います。
何とかホテルに辿り着き二ユースを見て驚きました。先ほどまで居た慰霊碑の下流側にあたる地区に鉄砲水が発生し、現地の方が亡くなったと言う事でした。一歩間違えば我々が被害に遭ったかもしれず、思わず天に感謝したことを覚えております。こんな雨の中でもナーダムは続行され、それが一晩中TVで放映されておりました。確かに子供たちによる競馬(距離20km)や流鏑馬そしてモンゴル相撲は血沸き肉躍るイベントではありました。
何時から世界の隅々までこの様な豪雨が発生するかですが、確実に言えることは温暖化が声高に叫ばれる頃からだと言う事です。いつの間にか日本も40年前のフィリピンと同じようになってしまったのです。我々は何もフィリピン化することは望んでおらず、昔のような「三夏」と呼ばれていた頃までで結構ですよ。爽やかな初夏から梅雨の蒸し暑い仲夏へ、そして暑さの厳しい晩夏へそして立秋を迎えるあのパターンですよ。
降る雨も凄いですね。わが国に下水道の技術が入って来た頃の設計基準の雨量強度は一時間で30mmでした。当時は都会でも田畑や空き地があり、降った雨のその一部は地下浸透し地下水の基となっていたのであります。それが住宅が立ち並び舗装された街並みが形成されると、降った雨は地表を流れ30mmで作られた下水道では処理できず、市街地に流れ込むことになった訳であります。これではいかんと設計雨量を50mmに変更したその頃から、時間雨量が60mmから100mmもの豪雨に襲われるようになりました。
時間雨量強度とは時刻で言う一時間ではなく、所謂一時間に最強に降った雨の量で、10~30mmは強い雨の部分に属し土砂降りもこの範囲に入ります。傘も役に立たず路面には水たまりが出来ワイパーも効果が薄いとされております。30~50mmはバケツをひっくり返したような雨で道路が川の様になる状態を言うのです。下水道も設計雨量が50mmであれば何とか処理できますが、それよりも強いと非常に激しい雨と呼ばれ、滝の様に降る雨と言われており、下水では処理できない量になります。
それでは時間雨量を80mmにすればよいと言うのは早計で、これ程の下水管を地下に潜らせるのは不可能なのです。下水断面は直径4mを越え、地下に潜らせる事は至難の業となるのであります。本来ならば数年に一度あるいは数十年に一度有るか無いかで設計するより、洪水になった方が安上がりなのです。
令和7年8月14日 毛利