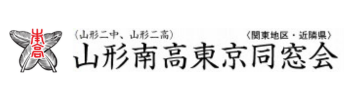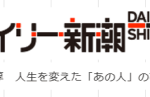皆さん、お元気ですか。先の通信で「男の美学」を取り上げたところ、以外にも好評で驚いております、しかし、世の中には凄い人がいるもんですね。例の連合艦隊司令長官だった山本五十六氏ですよ。彼は言ってますね「苦しいこともあるだろう、言いたいこともあるだろう、不満なこともあるだろう、腹の立つこともあるだろう、泣きたいこともあるだろう、これらをじっとこらえてゆくのが男の修行である」と何と「男の修行」ですよ。男の美学も大切ですが「男の修行」も心に響きますね。などと、山本五十六氏の言葉を切り口に、毛利のアドレス帳に載っている方々へBCCにて配信しております。メーリングリスト該当者は外したつもりでしたが、混入しておりましたらご容赦ください。
中国が「抗日戦争勝利80年」と言う事で軍事パレードを実施したとの事です。習近平国家主席は「世界一流の軍隊の建設を加速させ、国家主権を守り、領土を欠ける事無く統一しなければならない」などと演説したそうです。ロスケを代表してプーチン大統領と北朝鮮からは金正恩も参加して、仲の良さをアッピールしておりましたね。昔、悪の枢軸国と呼ばれた国がありましたが、その現代版ですね。もっと昔は、日独伊三国同盟などと徒党を組んで粋がっていた国もありましたね。何処の国でしたかと問われると、「恥ずかしながら我が国でした」と答えるしか術はありません。
中国は先の天安門事件で若者を血祭りにあげておりますし、ロスケはウクライナへ侵略し多くのウクライナの人々を虐殺し、子供をかどわかして自国に連れて行っております。北朝鮮は何を血迷ったのか、ロスケの先陣としてウクライナの前線に兵を送っております。彼ら、血なまぐさい国家元首たちが集ったところで世界は変わる訳がありません。しかし、彼らは「無かった事」にするのが得意な民族ですので気を付けましょう。
先の大戦の時ですら、今の中国軍(彼らは人民解放軍と名乗っておりますが)と日本の軍隊が共に戦った戦は殆どありませんでした。彼の大陸で日本軍と戦っていたのは蒋介石が率いる国民党でした。日本との戦争を勝利した国民党は、今度は紅軍と呼ばれた共産党の軍隊と内乱を起こし、最終的には毛沢東が率いる共産党が勝利し、国民党は台湾へと追い落とされたのであります。
こられの事実からも日本は中国共産党の軍隊とは交戦しておらず、彼らが主張する「抗日戦争勝利」は国民党が勝ち取ったもので、今の政権が勝ち取ったものでは無いのです。この辺りも中国は狡いですよね。あたかも自分たちが勝ち取った様なスローガンを掲げておりますね。そして映画や漫画による反日思想の植え付けですよ。
しかし、これ程まで日本を叩いて如何するつもりなのでしょうね。抗日を謳った軍事パレードでしたが、其処に参加した首脳は「血なまぐさい三人組」だけだったですね。彼らが拠り所としているBRICS(ブリックス:ブラジル、ロシア、インド、南アフリカ)からはロスケだけですし、インドは首脳会議だけは出席しましたが、パレードは欠席しており、ブラジルは高官の派遣だけだったですね。中国が投資している中南米や太平洋の島嶼諸国からはキューバ一国のみであり、太平洋の島嶼からは誰も参加すらしておりません。
いくら金をつぎ込んでも彼らは魂までは売らないのでしょうね。この事に気が付いてほしいのですが、もう戻れないのでしょうね。ついでに「お前たちの民族政策は如何なっているのだ。チベット民族やウイグルの人たちへの締め付けは何なんだ」と声高に聞いてみたくなりますね。ところがこれは内政の問題だと言って、彼らは人々の意見を聞きませんね。黒いベールに囲まれた彼の国の地域の中で、暴力と言論統制そして漢語教育の三つの矢でチベット人やウイグル人を責め立てているのです。それは現地に行ってみれば明白ですよ。
最初に侵略を受けたチベットの経緯は以下の通りであります。第二次世界大戦が終了した頃から、中国政府は政策的にチベットへ人(漢民族)を送り込み始めました。1949年に時のチベット政府はその行為に対し、漢民族の退去を求めたのであります。ところが、同年10月1日中国共産党は中華人民共和国の設立を宣言したのであります。設立と同時に「チベット人民を外国の帝国主義から解放する」との口実の下、チベットを中国の一部に組み込んだのです。
そして、チベットの首都ラサに人民解放軍を進駐させたのです。進駐に併せてチベット人を強制的に動員し、ラサへの公路の整備を始めたのであります。これ等の軍事支配に対し、1959年3月10日、チベット反共集団はダライ・ラマ14世を擁して反乱を起こしたのであります。戦いは装備に勝る解放軍の勝利に終わり、同年3月31日、ダライ・ラマはアッサム国境を越えインドに亡命したのであります。以来、チベットの自治を求める亡命政府との駆け引きが行われてきましたが、高齢となったダライ・ラマ14世に代わる後継者を巡って、中国政府との駆け引きが顕在化しているのであります。中国にとって、ダライ・ラマを抑える事はチベットを支配できる事に繋がるのです。
私がチベットを訪れたのは平成17年3月の事ですから、今から20年も昔の事になります。前年にチベットのラサと北京を結ぶ鉄道が完成し「チベット鉄道」と銘打って旅程を売り出したのです。まあ、易々と甘言に乗った私も軽率でしたが、矢張りチベットは当時でも秘境として知られ、一度は行きたい地でもあったのです。また、当時は僧侶で世界の探検家として知られる河口慧海の足跡を追っていた頃でもあったのです。
当時は、中国の強権に対し「焼身自殺」などと言う抗議運動も盛んな時でまだまだ自由な雰囲気は残っておりました。二度目に訪れたのがコロナ前の2019年10月でした。この時は霊峰カイラス山(6656m)を周遊する旅でしたが、この時は高山病に患かりラサに強制送還された事は報告済みです。軍民共用の飛行場からラサに戻った私は、ラサ市内を歩き回りました。何と言っても英語が通じない場所は気苦労が絶えませんでした。
しかし、市内には至る所に監視カメラが設置されており、住民の監視が行われておりました。レストランの中は言うに及ばずバスの中にまでカメラと録音装置が設置されており、行動はおろか会話までが筒抜けになっておりました。現地で「冬虫夏草」と言う漢方を買ったのですが、1gで7000円もしました。当時のゴールド1gと同じ価格でした。1gの冬虫夏草ですと3尾ほどになりますが、1尾を追加して4尾ほどにサービスしてくれました。今、ゴールドは1g当たり2万円を超えましたよね。凄いですね。冬虫夏草はどれ程の値上がりでしょうか。気になります。
令和7年9月30日 毛利