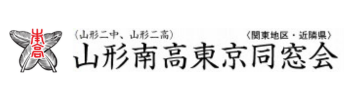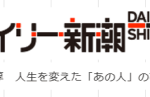皆さん、お元気ですか。東京の桜もそろそろ見納めです。今年の桜は卒業式から入学式まで咲き続けてくれましたね。今年の桜に「アッパレ」ですね。「散る桜 残る桜も 散る桜」ご存知良寛和尚の辞世の句ですね。「亡き友よ 残る己も 散る桜」とでも言いたくなるように旧知の友が亡くなっていきます。近頃は、家族葬で済ませたなどと葬儀の後に連絡が来ることが多く、悔しい思いをする事が有ります。まあ、時代なのでしょうね。などと、桜木に無常を感じている心情を切り口に、毛利のアドレス帳に載っている方々へBCCにて配信しております。メーリングリスト該当者は外したつもりでしたが、混入しておりましたらご容赦ください。
この欄で報告してある通り「旧甲州街道を歩く会」も、いよいよその最終回を迎えました。お江戸日本橋から信州の下諏訪まで53里24町ですから現代風に換算すれば約208kmとなります。長いですね。しかし、この間を昔の人は5~6日で歩いたとの事です。当時は一日30kmから速い人で40kmもの速さで歩いたことになります。凄いですね。
何故に甲州街道が整備されたかと言うと、江戸に幕府を置いた家康は甲斐の国・現在の山梨県を支配下に置いた訳です。この地を重視した家康は江戸から甲府に至る街道をも管理下に置きました。甲斐の金山などの鉱物を視野に置いたとか、江戸城の避難所としての役割もあったなどと言われております。まあ、こんな街道でしたが途中には小仏峠、笹子峠、富士見峠などの急峻な峠を越えなければならず、参勤交代でこの街道を利用したのは3藩だけだったとの事です。信州諏訪の高島藩と伊那の高遠藩それと飯田藩の山家のみだったとの事です。この事は、歩いてみれば納得です。
まあ、我々は一日せいぜい12kmから長い時で20kmほどとしてのんびりと歩きました。日本橋から歩きはじめ、最初の宿場町下高井戸までは都心を通りますから、町名の移り変わりが楽しかったですね。しかし、昔の街の名は廃止になっており、東○○町とか南○○町など東西南北に区切られた町名に変更になってしまいましたね。役所の連中にとっては支配しやすい町名かもしれませんが、町名に漂う風情が無いですよね。
歩いて分かった事と言えば、どの宿場町でも水が豊富で清流が流れていると言う事です。その清流を利用した小規模な水力発電装置も点在し、今でも使われておりました。水系的に分類すれば江戸は多摩川水系で秋川や野川が合流して水系を作っておりました。小仏峠を越えれば相模の国となりますが、彼の国は相模川が横断しておりました。旧甲州街道はこの川の河岸段丘に沿って作られており、景色も良かったですね。街道沿いには富士五湖からの桂川がその清流を見え隠れさせておりました。昔の旅人も癒された事でしょう。
甲州に入れば富士川です。街道一急峻な笹子峠を越えれば富士川水系です。甲武信ヶ岳を源とする笛吹川と南アルプスの名峰駒ケ岳を源とする釜無川が、甲府の南にある鰍沢で合流し富士川と名乗っております。街道は釜無川に沿っておりましたが、後方に富士山が聳え右には八ヶ岳連峰が我々を見守り、左側は鳳凰三山の奥に甲斐駒ヶ岳や仙丈ケ岳などの南アルプスの山々が顔を出してくれました。
最後の難所は富士見高原ですが、富士見峠を越えれば信州です。街道沿いの中小河川は諏訪湖を目指して流下し、諏訪湖に至りその諏訪湖を源流として太平洋に注いでいるのが天竜川となります。これ等の水系は清流が多く諏訪温泉の源泉までが無色透明となっておりました。清流を必要とする精密機械の工場がこの地に造られたのには、この様な背景があった訳であります。
日本橋から板橋に至り、軽井沢宿や沓掛宿を経て下諏訪に降りる街道が「中山道」であります。この街道は下諏訪で旧甲州街道を飲み込み、塩尻宿、奈良井宿、福島宿、妻籠宿、馬籠宿などを経て京都の三条大橋まで続いているのであります。宿場は69次で、日本橋から京都三条まで135里24丁8間で、現代風に換算すれば約533kにも及ぶ街道だったのです。東海道の様に河留めの多い大井川や、浜名の渡しとか桑名の渡しなど水による困難が無いと言う事で、女性の旅に好まれる街道だったとの事です。
全国にはⅠ万社以上もの諏訪神社があるとの事ですが、その総本山が信濃の国一宮である諏訪大社であります。諏訪大社とは上社本宮(諏訪市)、上社前宮(茅野市)、下社春宮、下社秋宮(下諏訪市)の四つの社からなる神社を総称した神社で諏訪湖の周辺に点在しております。七年に一度、奥山から神社の境内まで大木を曳いてきて建てる「御柱祭」が有名で、大きな見せ場である「木落し」が行われる木落し坂も有名ですね。
我々は春宮→秋宮→本宮→前宮の順で参拝しましたが、車ならともかく歩きの人は、下諏訪の春宮と秋宮あるいは茅野と諏訪市の本宮と前宮の何れかが選択され、四社を回るのは珍しいとのお褒めにあずかりました。尤も、春宮は宿泊した「ぎん月」の傍だったし秋宮はそこから歩いて直ぐと言う事でしたが、本宮の方は茅野駅まで電車で戻り、タクシーで本宮まで行き前宮まで歩きそこから茅野駅までタクシーと言う、年寄り向きの交通手段でした。
現地に行って気が付いた事ですが、諏訪湖周辺は茅野市、諏訪市、そして下諏訪市の三つの市に囲まれているのですね。特急「あずさ」は茅野駅と上諏訪駅には停まりますが、下諏訪駅には停まりません。街としては下諏訪の方が賑わっておりましたが、上諏訪駅はセイコーエプソンの本社を抱えているため、この地に特急が停まることになった模様です。この地は銘酒の産地で真澄、麗人、本金、横笛、舞姫、神渡,高天、御湖錦なる酒造会社が名を連ね、各神社には薦被りの四斗樽が奉納されておりました。当然、私の口にも奉納しました。
この地の春はまだまだの感じでした。桜は未だ蕾の状態で梅の花が満開でした。スイセンもこの世の春とばかりに花を結び、群生して咲いておりました。諏訪に入った4月4日は天候も良く、近隣の小学校の入学式へ向かう親子ずれに何組もお会いしました。「おめでとうございます」と声掛けをすると、揃って「ありがとうございます」と笑顔が返って来ました。歩いていて何か嬉しくなりました。こんな小さな喜びも歩く旅の醍醐味ですね。
令和7年4月15日 毛利