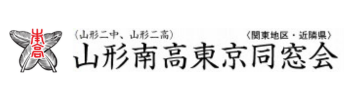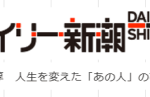皆さん、お元気ですか。5月から6月にかけて忙しい日々を送っておりました。ここで何とか一段落でホッとしております。東京も梅雨に入り雨の日が続いております。先日は老人会(PSAの会)の仲間たちと、明治神宮御苑の「花菖蒲」を観に行ってきました。アヤメもカキツバタも花菖蒲もすべて見ごろの一日でした。日本の梅雨も捨てたものではありませんね。などと、花を愛でに行った報告を切り口に、毛利のアドレス帳に載っている方々へBCCにて配信しております。メーリングリスト該当者は外したつもりでしたが、混入しておりましたらご容赦ください。
皆さんは「ドラゴンアイ」なる言葉をご存知でしょうか。山仲間では比較的通っている名称ですが、山の池や沼に積もった雪が溶けだす頃に現れる自然現象の事を言います。比較的高い山ともなれば冬には湖面も雪に覆われます。その雪が溶け出しますと、どうしても池の中央付近は雪解けが遅くなります。そうしますと、周囲の雪は溶けているのに、池の中央付近だけに残った雪が湖面から顔を出します。これが、あたかも目玉の様に見えるため「これは恐竜(ドラゴン)の目だ」と誰ともなく言いだした訳であります。
東北地方などの山麓あるいは山頂付近で池や沼がある場所はこの様な現象が起こりやすいと言えます。池の形が丸ければ丸いほど目の形に溶けやすく、人々はその神秘性に魅せられて見物に訪れる訳であります。但し、この雪解けの時期を推定するのが難しく、その年の積雪状況や気温の推移を睨みながらの推理となるのであります。
今回は、岩手県の北方にある「八幡平(1613m)」へ出かけて来ました。冬ともなれば樹氷のモンスターを見ることが出来ると評判の地ですが、この地に至る「八幡平アスピーテライン」が冬場は封鎖されるため、モンスターに会うのは難しい地域となります。八幡平地域は池や沼も多く、積雪も多いと言う自然条件が整っており、ドラゴンアイを見ることが出来る場として有名になっているのであります。因みにこの名称は海外の観光客によるものと言う事です。
今回は、このドラゴンアイを見るツアーで「神秘の絶景ドラゴンアイと新緑の奥入瀬渓流と三陸の歴史」と称するツアーへの参加でした。メインはドラゴンアイの観光ですが、それに色々な企画を追加し二泊三日の旅程に仕立て上げたものでした。この様なマニア向けのツアーに参加する人は少ないだろうと思っておりましたが、何と、18名もの参加者がありました。殆どが高齢のご夫婦でしたが、恐らく新緑の奥入瀬を歩くことに魅力を感じたのだと思います。その証と言っては何ですが、ドラゴンアイを観に行く途中は可成りの残雪の坂を登らなければなりませんが、その足元がおぼつかない様子でした。
三陸の歴史と銘打っている以上それらしき場所が有るのかと危惧しましたが、そこは手慣れた旅行業者の手中におちてしまいました。一極集中です。東日本大震災で被災した地の復興とかリアス式海岸の歴史など、東北には数えきれない遺構や遺跡が残っております。この中から復興は気仙沼一本に絞り、歴史は遠野と小岩井農園に絞り、移動をコンパクトに纏めたツアー設計でした。
東日本大震災の復興と将来を見据えた高速道路「三陸沿岸道路」あるいは「三陸自動車道」と銘打った道路が整備されており、宮城県から岩手を通り青森までの高速道路が出来ているのです。沿岸地帯の高台や北上山地の高所に造られたこの道路は、将来、東日本級の大震災が来ても大丈夫なように設計されており、現在の復興はもとより、将来の地震にも備えられる規模と強さを有しておりました。しかも、現在は復興中と言う事で料金も徴収しません。料金は無しで通行できるのです。復興の方々には申し訳ないのですが、旅行で使用しても料金は取られません。
宮城県気仙沼市は、東日本大震災の折には漏れ出した重油に火が付き、市内の殆どで被害を受けた街です。復興途中とは言ってますが、既に市内は整備され漁港の水揚げは日本一との事です。震災前は渡し船で行き来していた大島には、立派な橋がかけられており簡単に行き来が出来る様になっております。気仙沼湾の入り口には美しい斜張橋が聳えて我々を迎えてくれますが、大島へはこれまた美しい中路アーチ橋が架けられており、名称は「気仙沼大島大橋(愛称鶴亀大橋)」との事です。一見する価値のある橋梁たちです。
気仙沼港は我が国有数の漁獲量を誇り、特にカツオの漁獲量は日本一との事です。他にもマグロやサンマそして鮫が有名との事でした。身はすり身にして蒲鉾にしたりしますが、一番の名物はフカひれとの事です。中華などに含まれるフカひれは美味しいですよね。まあ、そんな事は如何でも良いのですが、湾内に張り巡らされている筏では、牡蠣や海鞘(ホヤ)などの珍味が養殖されておりました。この海鞘の刺身が美味しいのですが、まだ時期が早かったと見えホテルの食卓には並びませんでした。残ねん!三陸方面に行きましたら是非、海のパイナップルと言われる海鞘をご賞味ください。
岩手の歴史と言えば「遠野」でしょう。遠野物語などに出て来る曲り屋でしょう。県内に点在する曲り屋を一か所に集めて展示している施設も見学しました。昔の人々が馬屋と自宅をL字型に並べ、馬と共に生活していた家屋の事です。殆どが正面に母屋を築きその左側に馬屋を備えている形が大半でした。その中の一軒には馬が飼育されており、我々に愛想を振りまいておりました。見慣れたサラブレッドではなく、脚の太い農耕馬でした。園内には桐や藤の花が咲き乱れ、池には花しょうぶが花を結んでおりました。落ち着きますね。
私は二度目になるのですが「小岩井農場」も見学させて貰いました。何でも明治21(1888)年に当時の鉄道庁長官の井上勝が、日本鉄道会社の小野義眞と実業家の岩崎弥之助に諮り造られた農園との事で、3人の頭文字を取って小岩井と名付けたとの事でした。岩崎弥之助はⅠ万円札の岩崎弥太郎の弟ですよ。古くに建てられた施設であるため、その多くが「国指定の重要文化財」として指定されており、現地のスタッフがバスの乗りこんでの案内でした。2700頭に及ぶ乳牛の搾乳や彼らの糞を集めて処理する近代的な施設も案内して貰いました。重要文化財の建物は現在でも現役でした。この様なツアーは旅行業者を通さなければ出来ないとの事でラッキーでしたね。(この項続きます)
令和7年6月15日 毛利