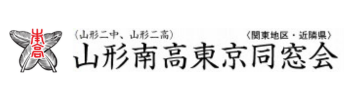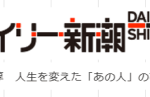皆さん、お元気ですか。ようやく梅雨も明けましたね。そして参議院の選挙とイベントが続きましたね。そして今日は私の誕生日ですよ。えっ、幾つになったかですって、恥ずかしながら82歳ですよ。別に恥ずかしい訳では無いのですが、歳の話は何となく照れ臭いですね。何の変哲もないこの日が、英国の皇太子ジョージ君が生まれた事で、世界の人々から祝福を受ける日となりました。ジョージ君も今年で12歳ですよ。私と70歳も違うのですね。70年ですよ、凄いですね。などと、私の誕生日の話題を切り口に、毛利のアドレス帳に載っている方々へBCCにて配信しております。メーリングリスト該当者は外したつもりでしたが、混入しておりましたらご容赦ください。
「汽笛一斉新橋を はや我が汽車は離れたり 愛宕の山に入りのこる 月を旅路の友として」ご存知「鉄道唱歌」の一節でしかも1番です。この歌は、明治33(1900)年に発表された唱歌で、第1集「東海道編」、第2集「山陽・九州編」、第3集「奥州・磐城編」、第4集「北陸編」、第5集「関西・三宮・南海編」と五つもの編に分かれて発表されており、作詞が大和田建樹で作曲が多梅雅(おおのうめまさ)と言う方々との事です。第1集の東海道編ですら、新橋から神戸まで66曲もあると言う事です。
本紙を作るにあたって66曲に目を通してみました。わが国の地理と歴史の勉強になりますね。鎌倉幕府と源頼朝の歌があり、織田信長の桶狭間や、徳川が天下を取った関ヶ原そして永遠の都・京都など目に浮かぶ風景が歌われております。暇な折り(本紙は暇な人が読むことを前提にしておりますので、お忙しい方はご容赦下さい)にはネットで直ぐに検索できます。試してみて下さい。
当時の新橋駅は現在の駅舎より東方にあり、駅舎の有ったと言われる地に、当時の駅舎が復活されて残っておりますが、石積みの重厚な造りに驚かされます。その地域一帯が「汐留地区」と呼ばれ、以前は国鉄の操車場だった場所の再開発が進んで四半世紀が立ちます。超高層のビルが林立しタワーマンションが脚光を浴びる切っ掛けになった再開発でもありました。
今でも高い評価を受けるオフィス街や住戸もありますが、ホテルの多さに驚かされます。今年のMLBでドジャース開幕戦は東京で行われましたが、大リーガーの方々や家族が泊ったと言うホテルを始めとし著名なホテルも点在しております。考えてみれば、明治の頃から旅の原点だったのですね。
当時、新橋を発った列車は一部区間を海の上を走らされていたと言う事です。海の上などと書くと船に出も載せてたのかと勘ぐる方もお在りかと存じますが然にあらず、用地買収の困難な陸地を避けて、浅瀬の浜に盛土をして石垣で固めた堤防を築き、その上に線路を引いたと言う事です。当時でも敷地の買収には苦労をしていたのですね。この英断を下したのが大隈重信で「陸蒸気(おかじょうき)を海に通せ」との号令の下、工事が行われたと言う事です。
この折に、海上に築かれた石垣が高輪築堤と呼ばれるものです。この高輪築堤は、現在のJR田町駅付近から品川駅付近まで27kmに渡って築かれたとの事です。平成31(2019)年の品川駅改修工事の際に見つかり、大きな話題となりました。新橋を発った列車はこの辺りで海の上を走り品川へ向かったのです。
開業時の新橋から横浜までの運賃は上等、中等、下等の3級等制で、上等が1円12銭5厘で、中等が75銭、下等が37銭5厘だったと言う事です。今の金額に換算すれば、当時はコメ10kgの値段が約55銭だったと言われており、換算すれば上等が1万5000円程度で、中等が1万円、下等が5000円程度だったと言われております。これを見るとべらぼうに高いですね。それでも人々は着飾って列車に乗っておりました。微笑ましいですね。因みに現在の運賃は片道490円とべらぼうに安いですね。
令和2(2020)年に、山手線で49年ぶりに新しい駅として開業したのが「高輪ゲートウェイ」なる新駅です。これで山手線の駅の数は30駅となるのですが、29番目に開業したのが「西日暮里」駅で昭和46(1971)年まで遡るのです。昭和46年などと言うと、東京に出て来て間もない頃で、夜の大学を卒業した直後でしたね。あの頃は何も考えずに遊び歩いていた頃です。従って、新しい駅が出来ようが出来まいが、一切関心がありませんでした。
不思議に思われるかもしれませんが、当時、私は都立工業高校の教員として勤めておりました。何せ新卒のまま教員になったため、理論上は説明のつく授業は展開していたつもりですが、話の持って行き方に自信がありませんでした。そこで、何方かの授業を参考にして教え方を工夫しようと考えたのです。別に編入試験を受けるまでもなく、聴講生として大学に行き講義を聞くだけでも良かったのですが、成り行きで編入試験を受ける事になった訳です。
それから猛勉強でしたね。数学の先生に頼み込み傾向と対策を始めました。数学の先生は「偏微分」は出ないだろうとの見解でしたが、私は出ると踏んで勉強してましたら、設問数が7問でしたが、その内4問が偏微分を駆使する問題であとは幾何と行列の問題でした。見事に「ヤマ」が当たり合格した訳ですが、前の学校との単位換算で「優」と「良」しか認めない、と言う事で、大半の単位を「可」で通過して来た私は、逆風の憂き身を味わうことになる訳です。因みに当時の学位は優、良、可、不可の4段階評価で、不可のみが不認定となる仕組みでした。今は如何なっているのでしょうかね。
3年生への編入学ですから2年も有れば卒業に至る訳ですが、認定してもらった単位数では2年は無理で3年は掛かるとの結論でした。辞めようかと思ったのですが成り行きで通い始めたら学校が面白くて仕方がありませんでした。生まれた初めて学校が面白い処だと気が付きました。それと、夜間の大学ですから皆さん務めを持っている訳です。その様な仲間と語り合ったり飲んだりしておりましたが、どんなに遅くなっても帰路は充実しておりました。この間に培った仲間との友情は今でも続いております。良い3年間でしたね。
当時は理工系で土木の講座を持つ夜間大学(いわゆるⅡ部)は都立大、日大、中大、攻玉社、関東学院など複数の大学が開校していたのですが、今は、土木建築などの講座を持つ理工系の大学は皆無で、辛うじてⅡ部を残している大学は東京電機大学のみとなっております。昔は、向学心さえあれば何処へ行っても学ぶことが出来たのに残念ですね。それとも、今は、夜学で苦学するなどと言うのは流行らないのですかね。面白いのにね。
などと、今回は鉄道唱歌から私の昔話へ展開してしまいました。読み流してください。
令和7年7月22日 毛利